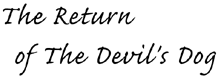Coral Fung -11
一ヵ月後―。
同僚達の燻らせるメンソールの煙草の煙が立ち込める楽屋の鏡の前に座って、俺は化粧の最後の仕上げに取り掛かっていた。
眉は弓形に細く長く。イメージはバロック調の恋する小悪魔。ウイッグは自分の髪と同じブロンドのストレート。今までのビッチのイメージにはほど遠い。ミゲルのお奨めの品だった。
瞼にはドレスと合わせたラメ入りの翠のアイシャドウを入れてあるが、その色合いは以前よりもずっと控えめだ。ベルンハルトがほめてくれた、目元を飾るラインストーンを右の目じりに三つ、丁寧に貼り付けた。照明を浴びて俺の顔にセクシーな影を落としてくれる重ね付けの付け睫の上から黒い縁取りのアイラインを入れた。目じりをぼかすと俺のきつい顔は少しやわらかく見える。
唇のラインに沿って描くリップラインは、上品なローズレッド。 唇にのせるのはパール入りのベビーピンクのルージュに変えた。最後に淡いばら色のチークを入れて、準備完了。
首筋にこれでもかと言うほどに吹き付けるのは先週ミゲルのところでベルンハルトと選んだDior Me,Dior Me Not。甘い香りが辺りに漂う。
あれからこの店も変わった。VIPシートは向こう一年貸切だ。予約した奴の名前はベルンハルト。いつだって客はお忍びで―あれ以来ベルンハルトは適度に仕事をバックれるってことを学習した。その効果たるや目覚しいものがある。何しろ俺たちはショーの後に二人きりで食事に出かけたりしてるんだから―やって来るベルンハルトか、何をどうやってそうなったのかは想像したくも無いが、堅物のハルトヴィックとフラウ・ミケイラだった。
フラウ・ミケイラの新しい恋についてはノーコメントだが、俺はとても満足していた。
むこう1年VIPシートを予約してのけた男。
俺は彼が来てくれるんじゃないかと毎日のショーを、仕事を待ちわびる様になっていた。
彼は俺に一枚のカードを渡していた。陸軍の紋章が物々しく金箔押しでカードの右端に刻印されていたから、それが“ベルンハルト陸軍大佐”の公式な名刺だってことは俺でもすぐに分かった。この世にそれを持ってる奴がいったい何人いるのか、おそらくそれを数えるのは難しくないってくらい貴重なものだってことも。俺の方から電話をすることもあったけど、彼も暇を見つけては俺のところに連絡をくれるんだ。
ベルンハルト。掴めない陸軍大佐。堅物のベルンハルト。そして、俺と同じセクシャリティの持ち主。目下、俺がこの世で一番惚れてる相手さ。
「クリストフ。そろそろ出番だわ。行きましょう?」
ジュスティーンと俺はお互いに手をとりあい、雑然とした楽屋から照明で目がくらみそうなステージへと、いつものように向かう。
「おいクリストフ!今日のVIPは」
「分かってるよ、レオナルド。ベルンハルトが来るんだろ、夕べ彼が電話で言ってた」
鼻につくイタリア訛りのドイツ語もまったく気にならないほど今の俺は寛容だ。
しばらく気まぐれなビッチは廃業だ。これからは恋に夢中なベルリンの歌姫としてしばらくやっていくことに決めた。
それが俺がこの街で見つけた本当の仕事だと思えるようになったから―。
〔Fin〕