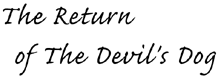Coral Fung -06
安物のウォッカと安物のトニックに、けちな薄切りのしなびかけたライムを一搾りするとどんなものが出来るか、試してみたことってある?
もしも効率的に絶望的な二日酔いになりたいって奴に勧めるとしたら、これほどにうってつけなものは無いような気がする。もちろん味については言うまでも無くて、本当に、本当に最悪だけど。
あれこそまさしく「クソよりはまし」って代物だ。
その”クソよりはまし”なウォッカトニックのお陰で、憎たらしいほど正確な4つ打ちのリズムでがんがんする頭を抱えながら、正午過ぎ辺りに漸くベッドから這い出し、身体にぴったりとまとわりつくドレスを脱ぎ捨てた。舞台衣装ってやつは二日酔いの休みの朝にベッドの中で着てるものとしては、全 く適していないんだ。 そうしてやっと窮屈きわまりない衣装と、化粧を落とさず潜り込んだお陰でカンディンスキーのキャンバスみたいになっているベッドから脱出した俺は、そのシーツを引き剥がし、バスルームに死にかけた熊みたいな歩き方で向かった。熱いシャワーを20分ばかり浴びれば”厚化粧の生ける屍”から”普通の役立たず野郎”位までには社会復帰が果たせる。
「何だよこれ?」
シャワーのお陰で、化粧と汗でべたついていた肌と、うんざりするような頭痛から解放された俺がまず最初にやったことは、雑然としたキッチンの片隅の古い型式の冷蔵庫の重たい扉を開けることだった。
中にはガス入りのミネラルウォーターのボトルと缶ビールが2パック、それに皿に載せた侭、エジプトのミイラもかくやの勢いで干からびた安っぽいハムが数切れ。我が家の食糧事情は実に深刻な局面を迎えて居るって言う、揺るがしようの無い事実を目の当たりにさせられてボクサーショーツにタオルを首から掛けただけの間抜けな格好で俺は思わず呟いた。
本当なら昨日は仕事が終わったら大人しく家に帰って、深夜営業のスーパーマーケットで冷凍食品を買い込むって算段をしてたんだっけ。ゲネラーレの奴が店にさえ来なきゃ、ジュスティーンをつきあわせて朝まで飲んだくれるような事も俺はしていなかったんだから。
思い出して俺は思わず舌打ちを一つ。
そうだよ。
「またあいつらの所為、かよ」
あいつら、と言うよりも俺にとってはゲネラーレとわざわざ名乗ってきたあの男の方が問題だった。昨日ジュスティーンとどんなに大騒ぎしても、ふっと我に返るたびに頭をちらついて離れなかった、あいつの顔がまた脳裏をよぎる。
立派な軍人。成功した男。誕生日を部下とその婦人達に祝われる理想の上官、あるいは、ただ単に「鼻につく肩書きの買い出し妨害野郎」。まだ俺の頭からこびりついて離れないあいつの顔が、あいつの存在が、苛立たしくて仕方が無い。
「俺の休みを返せって言うんだ!」
古びた冷蔵庫の扉を盛大な音を立てて閉じる。キッチンから一間続きになっているリビングの古ぼけたソファーの上に脱ぎ捨ててあった、セコンドハンドの色褪せた501と、洗いざらしのTシャツを身につけた。
食いはぐれた遅い昼食を、調達しなくちゃならない。
********
「ナイトメア」がある辺りのすぐ近くで必然的に男相手に商売をしているか、或いはゲイそのものの連中がほとんど、そんな街に俺は住んでいる。借りているのは広くも無く、新しくも無くて、ただ地の利が良いってだけで いつでも部屋は俺みたいな仕事の連中で一杯ってタイプの薄汚いフラットで、周りは、まぁ有り体に言えば安い酒と安い飯、そしてそれと同じくらいに柄の悪い話には事欠かないような場所だって言えば分かりやすいと思う。
くたびれた白いスタンスミスのソールで、ほこりっぽいアスファルトを踏みしめる。俺はドイツ語でも英語でも、アルファベットですら無い看板を掲げた店が何の違和感も無く溶け込む、雑然とした、どこかけだるいようなこの裏町の通りを歩いていた。材料を調達して家で料理するって言う気力も起きなくて、まずは腹ごしらえの為に、給料が入った時に良く寄る小さな店−ここのチリビーンズは悪くない。 その代わりミートローフは目の前が暗くなる程まずいんだけれど−に入ろうとした時に、隣の古道具屋の店先から聞こえてきた会話に俺は思わず、店のドアに伸ばした手を止めた。
「勘弁してくれよ将校さん。カードなんて、ウチは扱ってないんだ」
クーダム辺りの気取った店の店員なら卒倒しそうな態度。手首から両肩までびっしりと刺青を施した店主は何度か一緒に飲んだこともある顔見知りだ。明らかに客を「いやがって」居るのが分かる。
そもそも、古道具屋なんて言えば聞こえは良いけど、其処が故買品の類を扱ってるってのは、この辺りじゃ公然の秘密だ。何処の世界に盗品かもしれない物をカードで買おうとする奴が居るって言うんだ?
「だが、このミロの画集は素晴らしい。せめて取り置いて貰えないか?」
「取り置き?無理だね。取引は現金、その場だけ。分からねぇのか?それとも何か文句でもあるのかよ?」
店主が明らかに苛ついている。当たり前だ。この界隈でカードで買い物するなんて、スキミングされたいか、あるいは何か目的があってそうする奴か、どちらかしかいない。俺は物見高い表情を隠さずに、道具屋の店先へと顔を向けた。
「嘘だろ?」
頭の中にスローモーションのように記憶の断片が浮かび上がる。
−きっちりと着込んだ制服。胸にはいくつもの勲章。
−目深に被った軍帽。
−歳相応に肉が落ちて、成熟した男らしさがより強い印象の頬。
−繊細そうな顎。
−軍帽で隠れては居るけれど、睫は案外長い。
昨日の店の光景が。俺がVIPシートに入ったあの時の風景が、 まるで映画のハイライトシーンのようにフラッシュバックする。
薄暗い店の中じゃはっきりわからなかったけど、 こうして昼間の光の下でよく見ると、奴の軍服がVIPシートにずらり並んだ昨日の軍服連中の中で一番地味で、そして一番上等な生地で仕立てられてるってことがよく分かった。
そうさ。
俺の目の前にはあのゲネラーレが居たんだ。
「おい、アンタ!」
どうしてこんなところに?
そんな風に思うよりも早く、俺はこんな胡散臭い店で、悠長にあメックスのゴールドカードをちらつかせてる無防備で世間知らずな男の元に駆け寄っていた。
ゲネラーレは当然だが、突然自分に声をかけてきたこの俺を見て、訝しげに眉を寄せた。
−そのまま黙ってろ!
俺は道具屋の主人とゲネラーレの間に割り込みながら奴を睨みつけた。
「よう、ウルフガング!
こっちの将校さんには俺から良く言い聞かせとく。悪いけど、この場は俺に免じて、無かったことにして貰え無いか? 」
言葉が口から出てくるのと身体が動く方が早かった。
「何だ、クリストフ。お前の知り合いかよ?まったく、強情な将校さんだ。取り置きもカードもやってねぇっていうのに、がんとして譲ら無いんだぜ」
うでっぷしが自慢のウルフガングはスキンヘッドが自慢の大男だ。
「悪かったよ?な!頼むって」
「気をつけろって言って聞かせといてくれ」
「そうする。今度一杯奢らせてくれ」
そうして有無を言わせずゲネラーレの手首を掴み、昼からでもやっているバーに入る。昼からあいてるって他に何の特徴も無い店の、奥まったボックス席に無理矢理ゲネラーレを押し込めた。俺が奴の正面の席に陣取ったところで、漸くと奴は口を開いた。
「その、失礼だが。以前、どこかで会った事があったか?閲兵式か、何かで」
自分で自分を笑うしかなかった。そりゃそうだ。夕べの俺は「鋼鉄のビッチ・マリールイーズ」だったんだ。ウイッグも化粧もしてない今の俺が、あのドラァグクイーン本人だなんて、分かる訳がない。
なんと言う皮肉、なんて笑えない冗談だろう。つまり、ゲネラーレの前にいる俺は、−奴の仕事が具体的にどんな仕事なのか、想像もつかないが−奴の軍隊ならスカウトしたくなる様なただのマッチョ男だってことだろ?
俺はそれを良く良く理解していたつもりだったのに、それを忘れてこの男の顔やゲネラーレって呼ばれてたことを記憶していたってことに気がついた。他の客のことなんて、その日いくら使った位しか覚えていないというのに、だ。
「さあね、アンタの恩人さ。ウルフガングはマジで切れやすいんだ」
注文を取りに来た、客の忘れた煙草とミスオーダーのビールしか人生の楽しみが無さそうなバーテンダーにコロナを二本持って来るように言って追い払うと、俺は改めてゲネラーレの方へと向き直った。それは俺自身の途方もない気まぐれかもしれなかったが、このゲネラーレと素のままの自分―ただのクリストフとして―話をしてみたいと思った。
「言うとおり、君は恩人だ。礼を言わなければならない。まさかあんなすばらしいミロの画集に出会えるとは思っていなくて、先ほどの彼を不用意に刺激してしまった様だったから」
盗品まがいの画集に思いを馳せる顔には、ほんの少し前に自分がひと悶着を巻き起こそうとして居たことなんて微塵も感じさせなかった。
「礼なんていい。それより、アンタ、何でこんなところに?」
「休暇を部下と仕事の為に使うのを取りやめてね。
丸々1日のオフを手に入れたんだ」
丸々一日のオフ。そこだけは俺と一緒だ、俺は思った。バーカウンターに置かれた古いステレオ・セットからマドンナの曲がぼんやりと流れていた。
「ここが、アンタみたいな立派な格好をした人間が居るような街じゃないことはアンタだって周りを見れば分かるだろ。わざわざこんなに街に好んで迷い込んでくるなんて、物好きじゃなきゃ、男好きだ」
俺の言葉にゲネラーレはふむ、と首を傾けそして言った。
「どちらかな。ただ、一つ欲しいものはあるが」
「何だよ。さっきの画集か?
カードしか持ってないなら諦めろよ。今度こそウルフガングがブチ切れてアンタに殴りかかるぜ」
「そうじゃない。
私が欲しいのは自由さ。
街を歩く自由、街にあふれる自由を感じたい。
久しぶりの休暇を自分の好きに過ごしてみたい。
ああ、申し訳ない。自己紹介が遅れたな。私はフリードリヒ・ベルンハルト陸軍大佐だ。
フリードリヒと呼んでくれて構わないよ。
君の名前も聞いて構わないか?」
堅物の軍人のことだ。てっきりゲネラーレと呼べ、と言われると思い込んでいた。
「俺の名前はクリストフ。この街に住んでる」
俺のことをマリールイーズだと分かっていないのなら、それで良い。開き直りさ。自分の名前を名乗る俺は妙に冷静だった。そして同時に―夕べ、確かにゲネラーレと他の連中に呼ばれてはいたけれど―この目の前のベルンハルトがそこまで地位のある軍人だったなんて予想すらしていなかった俺は驚いた。だが、この手の連中って、普通は黒塗りの高そうな運転手つきの車を乗り回してるはずじゃないのか?
「アンタ、偉いんだろ?秘書とかさ、ボディーガードとかさ、そういう奴らがいつも周りについてるだろ?テレビやなんかでしか、見たことないけどさ」
なぜそんな重要なポストにある人間がたった一人でこんな場所をうろつこうと思ったんだ。運ばれてきたコロナの口に差し入れられたライムを引き浮いて、乱暴に搾りいれた。
「君の想像通り、私の周りにはいつも誰かが付いていて私を仕事から解放してくれない。
だが今日、多少は揉めたが―。どうにか、こうして一人で過ごす時間を手に入れたんだ。いったい何年ぶりか、もう自分でも分からない」
そういって静かに低い声でベルンハルトは笑う。手元の瓶は手つかずの侭だった。
「そこで、クリストフ、一つ君に頼みがあるんだが、聞いてもらえるか?」
「道案内か?ここから出る道ならすぐにでも教えてやるさ」
何を言い出すのかは分からなかったが、俺はひとまず空きっ腹をごまかすために、ライムを搾ったきりにしておいたコロナを勢い良くあおった。
「いや、違うな。クリストフ。私はもっとこの街を見たい。
君にこの街のガイドを頼めないだろうか?」
俺はベルンハルトの言葉に、盛大にむせ返った。喉を通り過ぎていく炭酸の、弾ける痛みにも似た感覚すら、この目の前のベルンハルトの仕業な様な気がした。
********
「ちょっと待てよ、何でそうなる!なんで俺なんだ。どうして!」
「この街が気に入った、とでもいうのかな。しばらくこの街を歩いて回りたい。それには私一人では分からないことが多すぎる。君は知り合いが多そうだし、この街のことを良く知っている筈だ。だから君にガイドを頼みたい。ああ、私もまだまだ捨てたもんじゃない、これはなかなかいい案だ」
威圧的でもなく、声を張り上げるでもない。きっぱりとした口調には迷いが無かった。
「冗談じゃない。今日は俺のクソ忙しい一週間のうちでたった一日の休みなんだぜ。何でそんな慈善事業をやらなくちゃいけないんだ」
それはアンタたちが外国に忍び込むときに使う方法だろ!西も東も軍人と警察の連中の考えることはどうしてこうも変わらないんだろう。何かの映画で俺は確かにそんなシーンを俺は見たことがあった。
「勿論、君の休みを不意にさせる気は一切ない。ギャランティはきちんと支払う」
たとえばコロナにはライムを入れた方が旨い、と言うのと変わらない言い方だった。当たり前の事の様にが呆気なく言い切るから、即座に「Nein」の一言が出ない。
俺の昼飯代はすでに二人分のビールに消えている。今日一日の出費を考えたってベルンハルトのオファーを受けたほうが明らかに俺の利益になるってことも簡単に想像できた。俺の妥協点が俺がこの役目を引き受けることにあるのは、ベルンハルトの予想どおりだった。
つまりベルンハルトのオファーはまさしく今日と言う日の死活問題に悩むこの俺にとって、Nein を言う余地を与えていないって事だ。
やけになって、残りのコロナを飲み干す。テーブルにたたきつけるように空いた瓶を置くと、忌々しいベルンハルトの手を突き出した。
「煙草が切れてるんだ」
「クリストフがガイドになってくれるのなら、私も心強い」
手の中に紙幣が数枚押し込まれる。言うまでも無く最高額面紙幣って奴だ。
こうして俺とこの風変わりな陸軍大佐の間には、とてつもなく奇妙な契約が締結されたんだ。