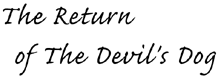Coral Fung -08
俺が向かったのは「フラウ・ミケイラの店」だ。
フラウ・ミケイラの店は色とりどりの衣装であふれている。ドラァグ用のドレスだけじゃない。ここにはおおよそこの町の連中が気に入りそうな服や帽子や靴が所狭しと並べられている。俺たちドラァグクイーンの舞台衣装から、モテたいと思う男達のものまで、このあたりに住んでるゲイの為の品揃えは完璧だ。
「あら、クリストフ。いらっしゃい。珍しい。素敵なボーイフレンドと一緒ね。一瞬ついにアンタも逮捕されたのかと思ったけど、そっちのボーイフレンド、警官じゃなくて、将校さんね?」
フラウ・ミケイラ−本名はミゲル・ナヴァーロ−この店の持ち主はラテン系の移民だ。金色に脱色した髪を短く切り揃えているなかなかの色男だが、5代ほど前の恋人との別れの傷跡−手の甲に入れたダサいトランプとダイスの刺青が自慢だった若いプエルトリカンは、自分の年上の恋人の病的とも言える浮気性に耐え切れなくて、ある日、街角で他の男といちゃついてたアンドレアスの首を切りつけたんだ−を隠すため、今日も黒いレオナルドフを首に巻いていた。
「なあ、ミゲル。こっちの将校さんに、何かみつくろってくれよ。こんな格好じゃどこにもいけやしない」
「”フラウ・ミケイラ”よ。もう、何回言っても覚えないんだから。でも、許してあげる。あたし、ハンサムな男に弱いの」
ミケイラはもみ上げから顎にかけて、顔の輪郭と同じラインに細く整えた髭を磨き上げた爪でなぞりながら、店の中にずらりならんだ商品を眺め、言った。
「ベルリン中のゲイがあなたの彼氏を見た途端にコックを勃たせる様にしてあげる」
*
15分後、ドレッシングルームからまず出てきたのはミゲルだった。
「クリストフ、見違えるわよ?あなたの彼氏」
そんなんじゃあない!と言い返す前にドレッシングルームのカーテンが開いた。
一仕事終えたミゲルが細い紙巻タバコに火をつけている。
「クリストフ、どうかな。自分ではよく分からないが」
そのとき、俺はすさまじい馬鹿面をさらしていたと思う。目の前のベルンハルトは、まるで別人だった。
軍帽で隠してた髪はきれいなブロンドで、元美容師のミゲルの手でモデルみたいにアレンジされていた。全身を包んでいた軍服の代わりにぴったりとした黒の開襟シャツと同じ色合いのシングルジャケット。長い脚を包むのはレザーパンツ。つま先からはイタリアあたりの伊達男が好みそうなしゃれた細身のブーツが覗いていた。
例えるとすれば、まさしく「ゲイ雑誌のピン・ナップ」そのものだった。
「変わるもんだな、ゲネラーレ・ベルンハルト」
それだけを言うのが精一杯だった。
「こんな格好、したことが無い。変に見えないか?」
「心配ないわよ。将校さん!とってもよく似合ってる。アタシが保障するわ。あっちの可愛くない坊やもすっかり将校さんに見とれてるわ。生意気な癖にこういうところだけ妙に初心なのよね、クリストフって」
ミゲルは満足げだった。奴のスタイリストとしての実力を別としても、とにかくこのゲネラーレが持っていた本当の魅力が引き出されていた事は揺るがし様の無い事実だった。
「ありがとう。彼のプライベートはよく知らないが、彼はとてもよくやってくれているよ。フラウ・ミケイラ」
「ねえ、どうせならアタシと楽しくやらない、将校さん?あんな生意気なクリストフと違って、アタシ、たっぷりサービスしちゃうから」
「黙れよ、ミゲル!新しい男にまで切りつけられたいのか」
「クリストフ!お代はこっちの将校さんからかっちりいただいてるから、アンタなんてもう用無しよ。二人で映画でも見てきたら?知ってる?3ブロック先のゲイシアター、新しい映画が封切りになってるのよ。それからパウルのカフェ、あそこのデカフェ(※カフェイン抜きのコーヒーのこと)、実は嘘っぱちでただのコーヒーなんですって、アタシ知らずに3回も頼んじゃったわよ。嫌だわっ」
「いこうぜ、ゲネラーレ。ミゲルのおしゃべりには終わりが無いんだ」
「フラウ・ミケイラ、私の軍服はどうなる?」
「あなたの立派なお衣装はちゃんとアタシが責任もってここで預かっておいてあげるわよ。今日は遅くまでここ開けとくから、安心して羽伸ばしてらっしゃい。良い男二人が仲良く歩いてて、やっかまれないかだけ注意しなさいよ。あんまりいちゃつかないようにね。男って嫉妬深いじゃない?アンタならよく知ってるわよね、マリールイーズ」
「ミゲル、絶対にアンタの男に全部ぶちまけてやるからな」
「あら怖い。でもアタシの今の彼氏、ドイツ語が良く分かってないから問題ないわ。彼、ベルリンに来たばかりなの。スペイン語ができるんだったら、お好きにどうぞ?」
*
手荒に閉めたミゲルの店の扉ががたと音を立てて揺れたが、もともと客から乱暴に扱われるように設計されてるに違いない。俺は気にも留めずに自分の姿にまだ慣れていないゲネラーレをつれて外に出た。
「クリストフ。これで私は部下たちにばれそうにないかな」
「当たり前だろ?どこから見たって」
俺は言いかける。どこから見たって”超イケてるゲイ”にしか見えないっていえばいいのか?俺は出かかった言葉をあわてて飲み込んだ。
「どこから見たって不良白人そのものにしか見えないよ。とてもじゃないがアンタが将校だなんて誰も思わないさ。良くてベトナムあたりから逃げてきた脱走兵のなれの果てだ」
「クリストフ、我が軍は過去にベトナムに派兵をしたことは―」
「歴史の授業なら遠慮しとく。いいから行こうぜ。腹が減ってるんだ。アンタのおかげで昼飯を食い逃してんだからさ」
*
ミゲルの店から少し行ったところに気に入りのケバブ屋街がある。その中でも何度か顔をだしてるトルコ人の店を俺は選んだ。
「ようクリストフ」
「ようオマム。久しぶりだな。ケバブを二つ。肉とチリソースたっぷりのやつを」
俺は見かけない”新顔”に早速アイサインを送るオマムとゲネラーレの間に入るようにして、両手にどでかいケバブを受け取った。オマムってムスリムだって言うのに、どうしてこうも見かけない男に色目を使うことに躊躇が無いんだろう。
「おい。クリストフ。食事、だろう?」
薄い包装紙越しにピタ・パンのぬくもりが伝わる。片方をゲネラーレに押し付ける。
「アンタと話すのにもだいぶ慣れてきたよ。いいか、これが俺とアンタの昼飯だ。行こうぜ、あっちに少しマシな公園がある。そこで食うんだ」
この街にも一応公園なんて代物がある。もっとも公園としての本来の機能が「市民の憩いの場」だとすればここのは「市民同士のいざこざか、麻薬の取引現場」としてその役割をまっとうしてるとしか言い様がないんだけど。とにかく俺たちは、コンクリートでつくられたでかい滑り台の横にあるベンチに腰を下ろし、買ったばかりのケバブにありついた。それは案の定うまくて、俺の胃は漸く人心地がついた。
「いつもは俺が見たことも無いようなすげえ高い飯を食ってるんだろ、アンタ」
「少なくともこれは初めて食べるものだな。だが、悪く無い。こんな風に食事を取るのも初めてだが。気に入ったよ」
きっと、ずらりと並んだナイフとフォークを使い分けるような、優雅な食事をしてるんだろう。ゲネラーレにとって、こんな場所で直接食べ物に食らいつくなんておそらく本当に生まれて初めてのことなんだろう。そして、おぼつかない手つきで肉と野菜でパンパンに膨らんだケバブを口にする姿は−俺は自分の頭がどうかしたのかとすら思ったが−妙に可愛くさえ見えた。
「なあ、いつも夕べみたいに取り巻きに囲まれて、一人で飯食ったことなんて無いんだろ?」
「私は自分のプライベートの時間に彼らの時間を犠牲にさせるつもりは無いから、自宅での食事は一人で取っているよ。仕事と彼らから解放されるのはいつも日の変わる様な時間だが、そこから先はとても、地味なものさ」
俺にとって、見たこともないような、どうやって食うのかすら想像すらつかない飯を、これまた俺には想像もつかない上品な会話を楽しみながら片付けていくってのは、それこそ日のあたる奴をあらわす分かりやすい光景だった。それが、一人で食事を?意外だった。
「一人でって、アンタ、家族は?」
「夕べ言ったように私に妻は居ないし、他の家族も、もう居なくてね。使用人が下がれば屋敷には私一人さ」
ベルンハルトの言葉は意外だった。俺の想像じゃこの手の連中はそれこそ年がら年中徒党を組んで居るはずだったから。そして、そう俺に言ったベルンハルトがどことなく寂しげな顔を浮かべたのを見逃さなかった。彼の表情以上に意外だったのは、それを見たこの俺自身に関して起きた心境―信じがたいことだが―についてさ。俺は彼のそんな顔を見てはっきり嫌だ、と思った。もっと分かりやすく言えば、彼にはこんな顔は似合わないと思ったんだ。さっき部下から逃げる時の様な楽しげな顔や、夕べ俺の店で俺達のドレス姿を眺める穏やかな笑顔、その方がどれほど彼に似合うんだろう。せめて俺がガイドとして雇われてる限りは、ベルンハルトにそんな顔をさせることが無いようにしたい、と。
だが、そのために俺はこの後、自分がどのように振舞えばいいのか、良く分からなかった。さっきみたいに故物屋巡りでもすればいいのか、それとも―この街にそんなものがあるなんて到底ない話だが―鑑定書つきの骨董品を取り扱ってる様な店を案内したりすれば良いのか?あるいはオペラ観劇か、美術館巡りか。自分の頭の中に浮かぶプランがこの街じゃ決して実現不可能なことであること分かっていた。だからなおさら、ベルンハルトがいったいこの街で何をしたいのかが分からなかった。彼は『自由』が欲しくて此処に来た、と言っていたが、俺はツアーコンダクタでも旅行ガイドでもない。具体的な要望ってやつを把握しておかなければガイドの仕事はできないだろう。
「なあ、ベルンハルト。アンタが此処で望んでる自由ってのがいまいち分からない。何しろこの街じゃ、皆好き勝手にやってる。アンタが求めてる自由ってのが一体何を指してるのか、皆目検討が付かないんだ」
俺の正体が”ナイトメア”の悪名高いビッチ・マリールイーズだとばれたことで、むしろ俺の心の中には晴れ晴れしいような感情が生まれていた。こんな気持ちになったのはこの仕事を始めて以来初めてだった。
「そうだな、マリールイーズ、いや、クリストフ。この街を歩いてみたいよ、自分の足で。いつも周りに部下達が居て、軍用車で街を移動するばかりなんだ。私は、自分の好きに店をひやかし、通りを歩く。そんなことに憧れてる」
この自由を求める偉大なるゲネラーレは俺がどうであれ−俺がただのクリストフであっても、あるいはビッチ・マリールイーズであっても−態度にも言葉にも微塵もゲイやドラァグに対する偏見を持っていない。俺にとってそれは今まで想像すらしていないことだった。そして、ベルンハルトは純粋に今この瞬間を心から満喫しようとしている。それも俺の想像を超えていた。
「いいさ。ベルンハルト。飯を食ったらそのあたりをうろついて映画館に行こうぜ。アンタが見たことも無い様なものをたっぷり見せてやるよ」
アンドレアスの店から歩いて10分も行かないあたりにある、ゲイシアターにベルンハルトを招待した。向かう途中、セコンドハンドの洋服屋を覗いて、ド派手なTシャツを物色し、立ち寄ったカフェではゲイショップに勤めてるその手の友達何人かとばったり出会って皆で下らない事で盛り上がり、話し込んだ。俺達の会話は―どこのバーにいい男が居た、とか、あのクラブでかかってた曲のCDを見つけた、とか―彼にとっては理解すら難しい話題ばかりだったにも関わらず、彼は楽しそうに笑った。コーヒーのとてつもない熱さに、ここがアメリカじゃなくてベルリンで、この店は命拾いしてるなと盛り上がった。まるで何年来かの知り合いみたいに。
そして、信じがたいことだが、この俺自身も最初は金の為に引き受けたガイドという仕事を楽しんでいた。何も無い街、何の希望も無い街。そう思っていたここが、実はそんなに悪くも無い場所だったんじゃないかとすら思えた。それは自分に正直になるのならば、ベルンハルトと過ごす時間そのものに俺が意味を見出し始めたって事だったたんだろうと思う。
散々寄り道してやっとたどり着いた映画館の客層は70%がゲイ、20%が俺と違って心も身体も完全に女になった連中、残りの10%は、俺みたいなどっちつかずのバイ野郎だった。上映してたのはアンドレアスの言う通り、俺も観たことが無かったフランス製のゲイ向けのラブストーリーだ。
「ベルンハルト、一つだけ忠告しとくぜ。絶対に俺から離れるな。俺達みたいな男が好きな連中から見た今のアンタは格好のファックの対象に見えるんだ。不本意なナンパをされたくないなら、絶対にだ」
「せいぜい君を失望させないように頑張るさ」
映画の内容は典型的なゲイ向けの映画そのものだった。強いて特徴を挙げるならベッドシーンがかなり多めで、それがベルンハルトにとってどう映るのかは分からなかった。
いかにも線の細い美青年同士の恋。俺達みたいな男と寝るのが好きな人間にとってはある意味理想的なハッピーエンドだった。濃厚なラブシーンも俺から見ればそれはそれで”幸せな光景”に見えた。
2時間たっぷり、ベルンハルトはおそらくこれもまた生まれて初めて見る光景を垣間見た。男達の多くはその間に行きずりのファック相手の物色に目の色を変えていた。ベルンハルトの反応は、おそらく今度こそ男が好きな奴らに対する嫌悪に満ちたものだろうと俺は予想していた。
映画が終わり、劇場内は明るくなる。とはいってもこれから後の男達のお楽しみの為にその明るさは推して知るべしだったけれど。
「ベルンハルト。これが俺達にとってのラブストーリーだ。幻滅したか?それともこれもアンタの言う自由に入るのか?」
「クリストフ、私は―。今日一日をこうやって過ごして、なぜ自分がこれまで独りで過ごして来たのか、分かってきた気がするんだ。そして、なぜ自分がこんなにも自由を渇望していたのかも。クリストフ、私は自分が求めていた自由がどんなものだったかということを、漸く理解できたと思ってるんだ」
「難しい話だな。男とファックしてみるのも悪くないと思った、とでも言うのかよ?俺を買うなら別料金だぜ」
「マリールイーズはそういう刹那的な行為を良しとしないと私は理解しているよ。だが、クリストフ、言うとおり…私は」
言いかけて、ベルンハルトは何かを考えるように形の良い唇を結んで息を吐いた。
堅物の将校、ベルンハルトがゲイである俺に対して何の偏見も持っていないって言うこと。そして、奴がこれまで独身主義を貫いてきた理由ってのがどうやらこのゲイ向け映画にヒントがあったってこと。ベルンハルトの胸の奥にある言葉を想像する。それが俺の考えてる結論どおりだと確信するには早すぎることは分かっていた。
だが、この男はただのスノッブな金持ち連中とは違う。節操なしのセックス中毒でもない。俺のことを気軽に買える手軽な相手だとも思っていない。俺のショーを純粋に楽しみ、俺のファンだとすら言った。
俺の気持ちが想像ができるか?
「寛容なんだな、ベルンハルト」
「これは寛容、と表現していい心境なんだろうか。私は寛容なんかじゃない、この年になるまでずっと、本当のことから目を逸らしていただけ、と言い変えた方が良いのかもしれん」
だが、次の言葉は俺の予想を大きく裏切るものだった。
「その前に、一つだけ。私は見知らぬ相手に脚を撫で回されるのは慣れていないんだ、クリストフ」
ベルンハルトと過ごしていた時間の楽しさに忘れかけていたが、この街は結局クズの集まりだ。
俺達はゲイカップルよろしく二人並んで座っていたというのに、ベルンハルトの隣にはいつのまにか男に飢えて仕方が無いってタイプの、ピアスだらけの痩せた男が居て、彼の引き締まった太腿に骨ばった手を伸ばしていた。
いつもなら何の気持ちの変化も起こらない。その時その時でつきあってた男がこうされてる風景を見たって動じたことなんてなかった。ことによってはそのまま3人で楽しもうとすることだってあったって言うのにだ。胸の中に怒りがこみ上げる。ベルンハルトに誰か知らない野郎が触れていると思うと自分を抑えることができなかった。それは以前、店で俺のドレスの中がどうなってるのかって事に異様にこだわった客をぶちのめしたときの気持ちと良く似ていた。
「ずいぶんいい度胸してるじゃねえか、このクソ野郎!」
俺はベルンハルトからそいつを引き剥がすと顎に一発、鳩尾に二発、最後に鼻柱へ一発をお見舞いした。俺のパンチは細身のその男からすれば重すぎたんだろう。男が鼻血を噴出しながら悲鳴を上げたのと、映画館の係員が飛んできたのはほぼ同時だった。薄汚い映画館の床に男の奥歯が、落ちたポップコーンの欠片みたいに転がっていた。