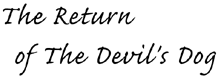Coral Fung -01
1992年・夏,ベルリン。
周りの同僚達の燻らせるメンソールの煙草の煙が立ち込める楽屋の鏡の前に座って、俺は化粧の最後の仕上げに取り掛かっていた。
厚地のファンデーションで塗り固めた地肌の上に、眉を弓形に細く長く。イメージはバロック調の色情狂。
俺の動きにあわせてきれいに波打つブルネットのウィッグが背中の真ん中辺りでふわりと揺れる。
このウィッグは割と気に入っていた。
何度もダビングされてノイズがさざなみみたいに入ったヴィデオ・テープで見たオードリー・ヘップバーンみたいになった気になれるんだ。
瞼にはドレスと合わせたラメ入りの翠のアイシャドウをたっぷりと。重ね付けの付け睫の先端には大粒のラインストーン。これは照明に良く映える。目元を際立たせる為に欠かせない、黒く太い縁取りのアイラインを上下の目の縁に引く。目じりのラインをギュっと上げるのがコツだ。それだけで気が強そうで、そのくせ気だるげな顔に見える。
リップラインは唇の外側くらいに大胆に描くのが丁度良い。色は輪郭を強調するような濃いボルドー。 唇にのせるのは通称”おしゃぶりレッド”。血のりみたいなグロテスクで暗い赤色のルージュだ。
最後にバカ濃いブロンズのチークを入れて、準備完了。首筋にこれでもかと言うほどにプワゾンを吹き付けた俺は、ボーイ長からなかば強引に取り上げてきた今日の席表に目を向けた。
「面白くないな」
店を仕切ってるレオナルドが、今夜も確実に金を使ってくれる客を上席に入れている筈だった。
一昨日は俺も雑誌で見かけたことがあるデザイナーとアシスタント、その前は有名な医薬品メーカーの御曹司と顔の良いボーイフレンド達。よくも金と暇をバランス良く−大体どっちかが有り余ってる奴はどっちかに飢えてるだろ?−持ちあわせてる連中がこんなにも居るものだと思う。
それに引き換え、俺は毎晩舞台に立ち、踊り、下ネタに満ちた意味の無い冗談を繰り返し、客に一滴でも多く飲ませようと躍起になっているっていうのにさ。
「どうしましたクリストフ?」
本人曰く「グレタ・ガルボへのオマージュを完璧に再現してる角度」で俺を指差してジュスティーンが言った。前髪を短くしたオリエンタルなボブ・スタイルのウィッグを飾るのはガラスの宝石をいやってほど埋め込んだ安物のティアラ。ボンデージ姿のミストレスをイメージした黒尽くめのエナメル製のタイトなドレスと、黒光りするピンヒールのブーツ姿はこの1年−つまり俺がこの店に立つようになってからというものってことだけど−見慣れた俺でもなかなか刺激的だ。
奴も俺と同じ様に出番待ちをしていたが、いい加減鏡の前に陣取って「セクシーに見える角度」の研究をするのにも飽きた様子だった。
俺を見て良い暇つぶしが出来ると踏んだんだろう。ジュスティーンは俺の隣にゆっくりと腰を下ろすと、俺のウィッグを整える。
知らずに唇についていた人造の髪が数本、ジュスティーンの黒いマニキュアの爪に巻き取られた。
「可愛い顔が台無しだわ」
「咥えるのが巧そうなら問題ないだろ。マダムで売ってるお前と違って、俺はビッチなんだから」
説明が遅れたが、俺たちはの仕事はドラァグクイーンだ。
この優雅なるマダム・ジュスティーンはこの仕事を離れてもこのままだ。つまりは絵に描いたようなオカマタイプの−尤もベッドの中じゃ立場は一転するらしい。さすがの俺も親友とファックしようとは思わないから、あくまで伝え聞いた話なんだけど−同性愛者だ。
一方の、ビッチ・マリールイーズことこの俺は舞台を降りればこの通りの話し方で、普段も格別女装したいとも思わない、男も女も抱くバイセクシャルだ。当然ジュスティーンにこうやって腕をマッサージされるのは嫌いじゃない。俺達にとってこうやって互いの肌に触れるのはちょっとしたスキンシップみたいなものだ。
「
ジュスティーン、席表みろよ。
また見世物見物のお偉いさんが来るみたいだぜ。ドイツ陸軍の軍服姿のやつらが出入りしてたよ。
レオナルドの野郎、俺がそういう客の相手が苦手だって、何回も言ってるってのに完全に無視しやがる」
店のブッキングと俺達のスケジュールを仕切ってるボーイのレオナルドはいつだって上調子だ。特に俺たちの仕事に関する要望と休みの話の切り抜け方は天才的と言える。
「そんな事、言わないで。皆クリストフがお目当てで来てるんです。分かってるくせに」
ジュスティーンの体温がサテンの布越しに触れて気持ちが良かった。
「それを言うならジュスティーンだってそうだろ。俺とジュスティーンでメインアクトを別の日にやったって構わな
いじゃないか。そのほうがお前に夢中なムッシュー・ドニだって喜ぶかもしれないし」
ソファが俺達の重みに小さく軋む。どぎつい演出で客を煽ってベルリンのゲイタウンで一番人気のこの店―"Coral Fung"―で、専属ドラァグクイーンとしてやっていくなら化粧が上手くて女っぽいってだけじゃ難しい。
俺もジュスティーンも身長は6フィート3インチはゆうにあるだろう。身体そのものも、おそらく世間一般で「マッチョ野郎」といわれる部類の男達と比べるとしても見劣りはしない筈だ。
ブロードウェイもかくやのきらびやかなステージに上がるドラァグクイーン達が鍛えまくった野郎ばかりとくればいやでも人目を引くだろ?
「冷たいのね。
私たち、良いコンビでしょう?
私たちは二人でいるから最高に見えるんです。クリストフはそう思わないの?」
ジュスティーンの踊りは最高にセクシーだ。
ジュスティーンはこの仕事を愛してるし、何より舞台で映える身体の大きさは誰にも負けない。俺とジュスティーンはほとんど同じ時期にこの店に来たが、今では俺達が二人で締めくくるっていう構成がこの店のショーにとって欠かせなくなっていた。
「ジュスティーン、クリストフ、もうすぐ出番だぜ!」
バウンサー兼ボーイのレオナルドが楽屋まで俺たちの出番を伝えに来る。イタリア訛りのドイツ語は相変わらず耳障りで、俺は毎回顔をしかめてやる。
「分かってるよ!」
俺は叫び返して立ち上がる。
もちろん優雅なジュスティーンの手をとって起こしてやるのは忘れない。
鏡の中にはドレスと化粧のけばけばしい俺がいた。
ビッチ宜しくスリットを大胆に入れた翡翠色のロングドレス。
かろうじてストラップが引っかかった両肩の筋肉が隆起している。肘まで覆った黒い手袋を少しつけ直して、グロスで光る唇を出番に備えてぱくぱくと動かす。
優雅で上品な物腰が売り、フランスからやって来たってふれこみのマダム・ジュスティーンと、気まぐれで冷たいベルリンのビッチ・マリールイーズ。
自分で言うのも変な話だが、俺達はこの店の「看板」としてやっていくには十分すぎるほど完璧だ。
尤も、俺とジュスティーンの仕事に、とりわけ客に対するスタンスは大分かけ離れていたけれど。
最後にちらりと鏡を見て咳払いを軽く一つ。
俺達はお互いに手をとりあい、雑然とした楽屋から照明で目がくらみそうなステージへと、いつものように向かった。